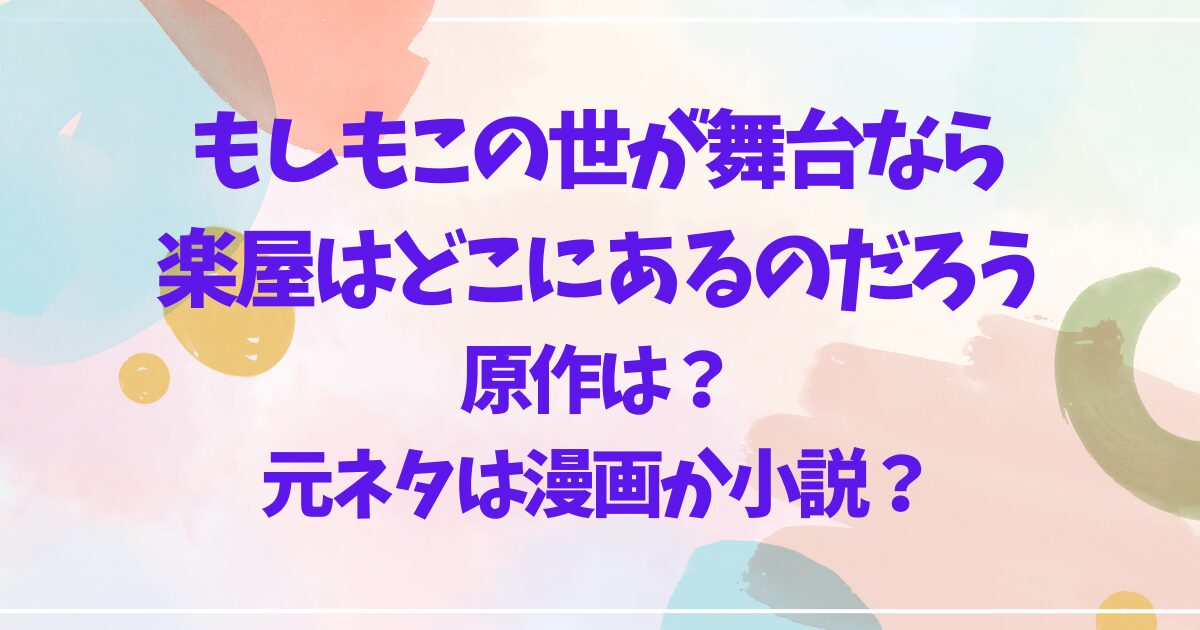2025年秋に放送される注目ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」。
このドラマでは、1984年の渋谷を舞台に、劇団を中心とした若者たちの夢・友情・恋愛・葛藤を描く青春群像劇が描かれます。
ドラマや映画が公開前に盛り上がるたびに、作品は漫画が原作?それとも小説?と気になる人が多い傾向です。
本記事では、この作品の原作の有無や元ネタとの関係性を徹底解説し、漫画・小説との関連、脚本の背景まで詳しくご紹介します。
・「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」の原作は?
・ドラマの元ネタは漫画か小説?
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろうとは?作品概況

まずは、「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」の基本情報をまとめました。
-
放送開始日:2025年10月1日より、フジテレビ系列「水曜10時(よる22:00)」枠にて連続ドラマ放送予定。
-
脚本:三谷幸喜。
彼にとって民放GP帯(ゴールデンプライム帯)での連続ドラマ脚本は約25年ぶりです。 -
舞台設定:1984年の渋谷。
若者文化が盛んであった時期、街には夢と焦燥、変化の予感が漂う中、演劇を志す人々、劇団での活動、恋、葛藤などが描かれる青春群像劇。 -
キャスト:菅田将暉(二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ほか)など。
菅田将暉が劇団の演出家の卵「久部三成」を演じます。
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろうの原作は漫画?小説?
近年、ドラマや映画で原作ありきの作品が多数を占めるため、「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」も漫画や小説があるのか気になる方は多いと思います。
そこで、本作の原作情報について調査しましたので詳しく解説していきます。
原作は漫画?小説?
「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」の原作についての公式情報および複数のニュース記事によれば、漫画や小説などの原作は存在しないようです。
また、三谷幸喜自身、「半自伝的要素を含む青春群像劇」という表現を使っていて、自身の体験等を元にした創作部分はあるものの、それが特定の小説や漫画を原作としているということはないようです。
そのため、「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」は完全オリジナルのストーリーということが分かります。
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう元ネタや類似要素はある?

「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」は、原作は存在しないものの、「元ネタ」や影響を受けた可能性がある要素はあります。
ここではそれらを解説します。
半自伝的要素
「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」では、三谷幸喜が自身の若い頃の演劇活動や、劇団に関する思い出を下敷きにしているとの報道があります。
創作ながら、彼の体験や思い入れを反映したキャラクター設定や舞台背景が含まれているようです。
1980年代の渋谷という時代設定も、実際に若者文化や劇場文化が盛んだった背景を再現しようという意図が感じられます。
演劇・劇団文化の参照
「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」の主人公が演出家の卵であることや劇団の舞台や楽屋の描写。
また、演者同士・スタッフとの人間関係など、演劇という“舞台裏”の文化や、演者の苦悩や情熱といったテーマがストーリーの中心になっています。
これは、演劇をテーマにした小説・漫画などに共通するモチーフです。
特定の漫画・小説との直接の類似は現時点では確認されていない
調査した限りでは、既存の漫画や小説で「演劇青春群像劇」「1980年代の渋谷」「演出家志望の若者」「劇団の楽屋裏」が完全に重なる作品は、公式に挙げられていません。
また、制作側も「原作なし」であることを強調しているため、既存作品の直接の翻案・引用ではない可能性が高いと考えられます。
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろうのような「原作なし」が注目される理由

「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」のような、原作なし、オリジナルドラマというスタイルには次のような特徴と利点があります。
- 視聴者に展開を予測させにくく、先入観なしに物語を楽しませることができる。
- 脚本家・演出家の自由度が高く、キャラクター設定や物語の方向性を固定の枠組みに縛られず創造できる。
三谷幸喜の“独自の世界観”“自分しか書けない物語”という意図とも合致する。 - “半自伝的”要素を含めることで、リアリティや感情的な深みが出やすく、人間ドラマとしての厚みを増す可能性がある。
過去のオリジナル脚本での成功例
実際に、過去には『オレンジデイズ』(2004年/TBS)や『逃げるは恥だが役に立つ』(2016年/TBS)※原作漫画ありだがドラマオリジナル要素で大ヒット
そして三谷幸喜作品では『王様のレストラン』(1995年/フジテレビなど、オリジナル脚本から社会現象となった名作も多数存在します。
こうした成功例は、「原作なし」だからこそ先が読めないスリルや、脚本家の世界観を存分に堪能できる点が魅力です。
「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」も同じく、予測できない展開の面白さと、三谷幸喜ならではの軽妙な会話劇に期待が高まっています。
オリジナルだからこそ生まれる“先が見えないドキドキ感”が、視聴者を惹きつける最大の魅力になるでしょう。
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろうの注目すべきポイント

ドラマ「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」が放送を重ねるにあたって、注目したいポイントをピックアップしておきます。
-
物語の“演劇”描写がどれだけリアルか
楽屋・劇団内部の細かい描写、演出家・俳優の関係性、舞台準備など、“舞台裏”のリアリティがどの程度かが評価されるでしょう。 -
キャラクターそれぞれの立ち位置
主人公久部三成だけでなく、ダンサーや放送作家、巫女など、異なるバックグラウンドを持つ複数の登場人物がいるため、それぞれの夢や葛藤がどのように交錯し展開するか。 -
「80年代渋谷」の再現
当時の街並み・若者文化・演劇界・劇場の空気など、時代描写が視聴の鍵。ノスタルジーだけでなく、その時代特有の若者の焦り・可能性・苦悩などがどれほどリアルに描かれるか。 -
三谷幸喜の脚本スタイル
会話劇・人物描写のテンポ・意外な展開など、三谷ならではの特徴がどのように出てくるか、特にこのテーマとキャストでどのように新しいものを作るかに注目。
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう原作は?元ネタは漫画か小説?まとめ
この記事では、新ドラマ「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」の原作は漫画か小説なのかについて調査していきました。
結果として、「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」は、脚本家・三谷幸喜自身の体験等を元に作成した”完全オリジナルストーリー”です。
そのため、元ネタとなる漫画や小説は存在しません。
三谷氏自身の演劇経験を反映した“半自伝的”要素も含まれており、これまでにないオリジナルドラマとして期待されています。